こんにちは!
大阪市西淀川区姫島にある「ひめじま本通整骨院 cure」です。
気温も暖かくなり、歩きやすい季節になってきましたね。
歩数が増えると起こりやすいのが股関節痛です。
今回は股関節痛の症状についてご紹介します。
【発生機序】
股関節は、骨盤の「寛骨臼」と大腿骨の「骨頭」から構成される球関節で、広い可動域と体重の支持という大きな役割を担っています。関節の表面は軟骨で覆われ、動きを滑らかにし、衝撃を吸収します。また、関節包、靱帯、筋肉、滑液包といった周囲の組織が関節を支えています。股関節痛は、これらの構造に損傷、炎症、変性が生じた場合に発生します。特に、軟骨の摩耗や骨同士の衝突、周囲筋肉の過緊張が痛みの主な原因となります。
【症状】
痛みの部位は主に股関節の前面、側面、または臀部に現れます。歩行時や立ち上がり時に痛みが強くなることが多く、進行すると安静時にも痛みが出現するようになります。また、関節の動きが制限される可動域制限、脚の引きずり、階段昇降の困難、さらには股関節の引っかかり感や違和感を訴えることもあります。慢性化すると、日常生活動作全体に支障が生じます。
【原因】
股関節痛の原因には多くの疾患や状態が関係しています。主なものを以下に示します:
変形性股関節症(OA):加齢や過去の外傷、先天性股関節脱臼などにより、軟骨がすり減って骨同士が擦れ合い、慢性的な痛みと可動域制限を引き起こします。
関節唇損傷:股関節の縁にある関節唇がスポーツや繰り返しの動作で損傷し、引っかかり感や鋭い痛みを伴います。
股関節インピンジメント(FAI):骨の形状異常により、大腿骨と骨盤がぶつかり、軟骨や関節唇を損傷します。
大腿骨頭壊死:骨頭への血流が途絶え、骨組織が壊死し、激しい痛みを伴います。
滑液包炎や筋膜炎:筋肉や滑液包に炎症が起こることで、痛みが発生する場合もあります。
リウマチ性関節炎や感染性関節炎:自己免疫や細菌感染による関節の炎症が原因となることもあります。
【対策】
まずは、正確な診断が重要です。整形外科でのX線、MRI、CTなどの画像診断により原因を明確にし、治療方針を立てます。治療は原因によって異なりますが、以下が一般的な対策です。
保存療法:安静、アイシング、消炎鎮痛剤の服用、関節周囲筋のストレッチや筋力強化(特に中臀筋や大腿四頭筋)を目的としたリハビリが行われます。また、体重管理も関節への負担軽減に効果的です。
物理療法:温熱療法、電気刺激療法などを用いて血流を促進し、痛みを軽減します。
装具の使用:股関節にかかる負担を減らすために、杖やサポーターを活用することがあります。
外科的治療:関節鏡による損傷部の修復、骨の形状矯正手術、症状が進行した場合には人工股関節置換術が選択されることもあります。
【まとめ】
股関節痛は、関節自体やその周囲構造に起こる異常によって発生します。痛みを放置すると、慢性化し、日常生活に大きな制限をもたらすため、早期の診断と適切な対応が重要です。日常的には、無理な姿勢や過負荷を避け、適度な運動と筋力維持を心がけることが予防にもつながります。
当院では治療だけではなく、自宅で出来るストレッチ等もお伝えします。
気になる症状がございましたら一度ご連絡ください!

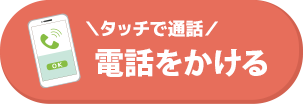
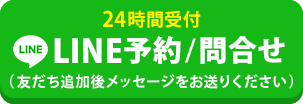





お電話ありがとうございます、
ひめじま本通整骨院でございます。